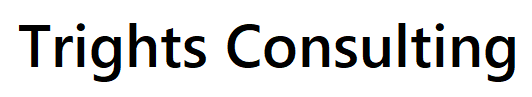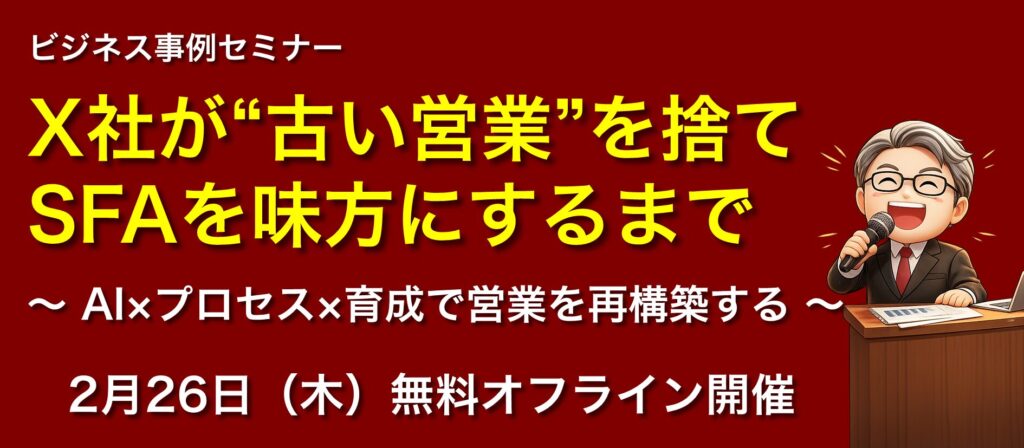この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です。
Googleトレンド分析で、日本における「セールスイネーブルメント」のWeb検索のボリュームを見てみると、10年前の2015年から始まりしばらくの間は何もなくずっと平坦で、2019年から2021年にかけて軽く注目が集まり、2022年ごろから一気に盛り上がりを見せて2024年にピークを迎えています。
実際に我々にご相談いただくことも増えており、ここ数年でセールスイネーブルメントに関する日本語の記事が一気に増えてきたように感じます。
そこで今回は、日本の営業でも当たり前のものになりつつあるセールスイネーブルメントに取り組むにあたっての大事なポイント、「成熟度モデル」をご紹介したいと思います。セールスイネーブルメントを取り入れ、自分たちの得意技として育てて営業の生産性向上につなげていくために何が大事なのか、一緒に見ていきましょう。
あらためて「セールスイネーブルメント」とは
本題に入る前にセールスイネーブルメントの定義について、改めて確認しておきましょう。セールスイネーブルメントとは、「営業活動を段階・プロセスごとに分解し、それぞれの段階・プロセスで使われるコンテンツやツール/システム、関連する研修などの各種施策を評価・改善して全体の生産性を高める取組」のこと。営業担当者個人やマネージャーの経験や優劣で評価するのではなく、施策側を数値的に評価して継続改善しようという考え方です。
このセールスイネーブルメントに取り組もうとすると、そもそも自分たちの顧客の購買プロセスを明確にし、それに対応する形で自分たちの営業プロセスを定義し、それぞれのプロセスに必要なツールや研修を準備したり、それらをマネジメントできるようなSFAやマネジメントツールを入れたりする、ということになっていきます。
ビジネスプロセスマネジメントの世界で一般的な「成熟度モデル」
以前からビジネスプロセスマネジメントの世界には「成熟度モデル」という考え方があります。業務の組織化・体系化を診断する指標なのですが、私はセールスイネーブルメントを取り入れていく上でも使えるものだと思っています。
そこでこの「成熟度モデル」の入門書である「The Basics of Process Improvement」から、基本的な考え方をご紹介しましょう。
1. 非公式:文書化されていないプロセスがいくつか存在し、個々の従業員の努力によって業務が実施される。
2. 文書化開始:いくつかのプロセスが組織化・文書化され、反復可能となり始めている。成功事例が出始めている。
3. 定義&統合:ほとんどのプロセスが定義・連携・統合され、標準的なビジネスプロセスとして共有されている。
4. 管理&部門横断化:プロセスは評価基準によって管理され、部門横断的に定義・運用されている。
5. 最適化&継続改善:継続的な改善を目的とした最適化の試みが定期的に実施されている。
「プロセス」という言葉を「営業施策」に置き換えれば即セールスイネーブルメントの成熟度モデルに使えるでしょう。成熟度3に「定義&統合」とあるように、個々のプロセスが個別最適化しないように関連付けることの重要性が述べられています。そして最後が「最適化&継続改善」で、一度整理されただけでなく、最適化の試みが定期的に実施されるというレベルになることが目指す姿だと思います。
セールスイネーブルメント向けの成熟度モデル
私がこのように考えていたところ、海外、特にアメリカの専門家たちによってここ数年、セールスイネーブルメント向けの「成熟度モデル」を整理しようという取り組みに出会うことが増えてきました。その中で一番シンプルで分かりやすいと私が思うモデルは、バイロン・マシューズ氏らによる「Sales Enablement」という書籍で定義されているものです。
1. 無作為:まだ存在していない
2. 整備 :部分的に存在する
3. 拡張 :体系化され、整合・連携している
4. 適応 :リアルタイムに改善され、顧客体験に焦点が当てられている
このモデルで注目してもらいたいのが、レベル3の「拡張」です。これは研修や営業ツール、マーケティングコンテンツ、SFAなどの営業の施策それぞれが単に整備されるだけでなく、体系化され整合・連携したものになっていなければならないレベルのことです。もともとのセールスイネーブルメントの定義では「各種施策を評価・改善して全体の生産性を高める」というレベル4の「適応」に強く焦点が当たっている面があり、その前段階としての「施策の体系化と、施策間の整合・連携」に焦点を当て直したとご理解ください。
こまめに業務要件を改訂することで、戦略の実現性を高めた事例
これらのモデルを具体的にイメージしてもらうために、私のサポートしている企業の事例をご紹介しましょう。
この企業では激変する環境変化に合わせて営業戦略や商品などを見直し、パイロット実践を経て現場に展開していく、という取組を2~3年周期で実施しています。新しい営業戦略や商品、そしてそれを効率的に営業するための手法やツールが現場で着実に実践されるために、手法をプレイブック化して組織内で共通言語化し、それを「業務要件」に反映させ、必要な研修を開発・提供し、実践結果を「業務要件」に照らし合わせて評価するというのが一連の流れになっています。
ここでポイントとなるのが、「業務要件」のこまめな改訂です。多くの企業、特に大企業では「業務要件」は一度決まるとなかなか変わらないものですが、この組織では、扱う商品が変化したり営業手法が高度化したりして営業担当者に求められるものが変わるたび、2~3年おきにこまめに内容を見直すということをしています。前述のモデルの「最適化&継続改善」ができていると言えるでしょう。
ここまでできてくると、「業務要件」に記載されているスキルや手法を体得されることを目的として研修が整備・提供されるので、メンバーにとって受講へのモチベーションも高いですし、マネージャーが自ら研修講師役を買ってでます。また、組織が定める戦略を実践して売りたい商品を売ることで、営業担当者やマネージャーが正しく評価されるようにもなっているという、戦略の実現性が高い状況を作れていると思います。
成熟度3「拡張」からいよいよ成熟度4「適応」へ
さらに最近では、「業務要件」の達成率と達成に至るまでの期間(速度)をベースにして、研修の内容やOJTの指導の仕方を見直すという活動も開始しています。
この状態を冒頭でご紹介したモデルに置き換えると、成熟度3の「拡張」(施策の体系化と、施策間の整合・連携)レベルから成熟度4の「適応」(リアルタイムの改善)になってきたと言えるでしょう。
この営業組織の取組はセールスイネーブルメントの成熟度モデルが発明される前から、先ほどご紹介したビジネスプロセスマネジメントの成熟度モデルを参考にして進めていたもの。これまで自信を持って実践してはいたのですが、セールスイネーブルメントという観点からお墨付きをもらえ、改めて一安心している状況です。部分的ではありますが、営業施策の体系化・整合・連携の例として、参考にしていただければ嬉しいです。
営業施策の個別最適の罠を回避するために「成熟度モデル」を取り入れよう
セールスイネーブルメントの重要性が日本でも広く認知されるようになり、営業向けの研修やツール、コンテンツ整備についてのご相談を受ける機会も随分と増えてきました。ただ、それらの営業施策が個別に設計されていたり、基本的な考え方や営業としての目指す方向性が一致していない、整合・連携していない様子も頻繁に見受けられます。そのような個別最適の罠に陥ってしまわないようにするために、今回ご紹介した「セールスイネーブルメント成熟度モデル」、特にその中でも成熟度3の「拡張」(施策の体系化と、施策間の整合・連携)という考え方は有用だと思います。
4月から新年度を迎えるにあたって、あらたにセールスイネーブルメントや営業施策の整備に取り組んでおられる営業組織も多いことでしょう。ぜひ皆さんの営業施策を今回ご紹介した成熟度モデルに当てはめてみてください。個々の施策だけでなく営業組織全体として取り組むべき、大事な課題が見つかるかもしれません。
参考:
「Sales Enablement: A Master Framework to Engage, Equip, and Empower a World-Class Sales Force」(Byron Matthews et al., Wiley, 2018)
「The Building Blocks of Sales Enablement」(Mike Kunkle, Association for Talent Development, 2021)
「The Basics of Process Improvement 」(Tristan Boutros et al., CRC Press, 2016)