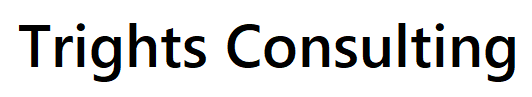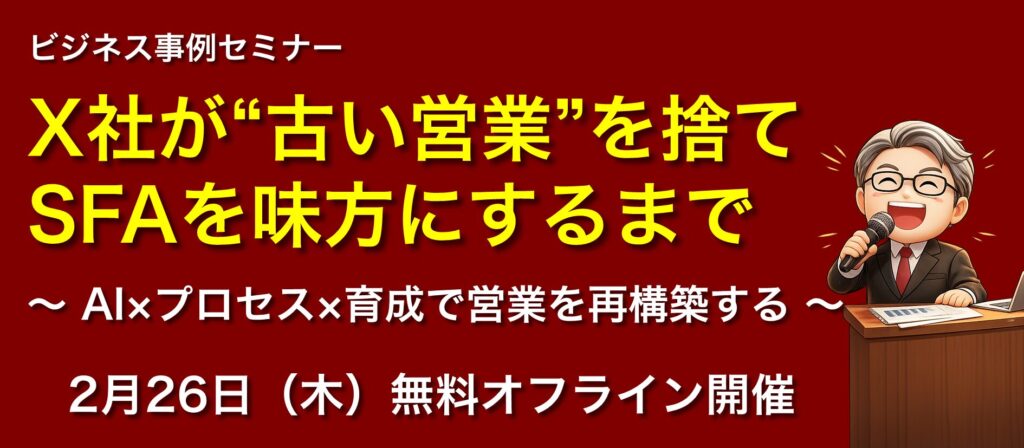この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です。
Web検索や生成AIの普及によって、製品の情報や利用者のクチコミなど、顧客が自ら必要な情報を得られるようになったため、以前あった営業担当者の情報優位性はもうなくなり、顧客が自ら購買プロセスを主導するようになっている。この状況において営業担当者に求められるのは、顧客の購買プロセスを後押しする「顧客中心営業」だ。
これまでこのブログで何度も取り上げてきた「顧客中心営業」というコンセプト。初出の2021年8月からの4年半でこのコンセプトに関連する記事が32件ですので、2か月に1度はこのテーマについての記事を書き続けてきたことになります。そしてこの4年半の間に、顧客中心営業というコンセプト自体が大きく進化/変貌を遂げています。
そこで今回は、これまで取り上げてきた「顧客中心営業」というコンセプトの進化の経緯と、最新の位置づけについてご紹介したいと思います。「顧客中心営業が大事だと思うが、具体的に何をしたらいいのかわからない」という方には格好のヒントになる内容が満載ですので、ぜひお読みください。
初出(2021年)時点のまだイメージがあいまいだった頃の「顧客中心営業」
2021年8月当時の「顧客中心営業」での営業担当者の役割はまだザックリとしか表現されていませんでした。以下が初出記事での、営業担当者の役割をまとめて表現したものです。
顧客の組織の中に入り込んで各関係者のニーズや課題を深く理解して、個別に最適な解決策を提示して、最適な購買を支援し、購買後も顧客の目的達成のためにサポートするという、非常に高度な役割が営業担当者に求められるのです。
原則としては分かるものの具体的にどうすればいいのか、2021年当時はまだこのイメージがあいまいなままでした。
2021~22年に優勢だった「インサイト提供タイプ」顧客中心営業
そのころ優勢だったのが、顧客が知らない知見や洞察を提供することで、顧客の購買プロセスを牽引しようという考え方です。2011年に出版された営業の名著『チャレンジャー・セールス・モデル』や、2022年の『Elite Sales Strategies』では、顧客が持っていない貴重な情報を提供することの有用性が力強く表現されています。後者から特徴的な部分を引用してご紹介します。
コンサルティング営業において大事なのは、解像度を上げて(Higher Resolution)顧客のビジネスや問題を見直し、それに基づいて新たな意味を与える(Sense Making)ことの2つだ。これによって問題の根本原因を見つけ、打ち手の確からしさを確認し、意思決定に自信を持たせ、顧客の購買を後押しするのだ。
最近は耳にする機会がずいぶん少なくなりましたが、当時はこのような専門的な知見(インサイト)を武器にする営業を「インサイト・セールス」と表現していました。しかし、2022年12月に生成AIが登場したことで、専門的な知見自体がコモディティ化してそれだけでは差別化できなくなってきた頃から、「顧客中心営業」がインサイト提供タイプから協業取組タイプへとシフトしていったのです。
2023年が転換点!「協業取組タイプ」顧客中心営業とは
ここでの「協業取組タイプ」がどういうものかというと、顧客に提供する情報/インサイトだけでなく、顧客の社内での合意形成のあり方や意思決定の仕方に対して直接的/間接的に関わっていく存在として、営業の役割を再定義したもの。この協業型取組のきっかけとなる2冊の本が2023年に登場し、2024年に入ってからじわじわと話題になってきたのです。
協業取組タイプその1:顧客と課題/解決策/購買プロセスを一緒に創る「共創型営業」
2冊のうち1冊が『Buyer First』。この本の中で提唱されている顧客中心営業のあり方が「共創型営業」(コラボラティブ・セリング)。ここでの共創(コラボレーション)がどのようなものか、以下抜粋をお読みください。
コラボレーションによって、顧客が抱えている「最も価値ある問題(Most Valuable Problem)」が何か、「最も価値ある商品(Most Valuable Product)」が何か、そしてそれを実際に購買するための「最も価値あるプロセス(Most Valuable Process)」が何かを明確にするのです。
この3つの「MVP」を明確にするための「コラボラティブ・クエスチョン」などの詳細は、ぜひ「新たな営業コンセプト『コラボラティブ・セリング(共創型営業)』とは」をお読みください。
協業取組タイプその2:顧客のキーパーソンと一緒に顧客社内の購買プロセスを推進する「共に売る」
そして同時期に発売された2冊目の本が『Selling With』(共に売る)というもの、これは顧客のキーパーソンと一緒になって顧客社内の購買プロセスを推進させて、顧客の購買活動を成功させようという考え方です。
商談の成否を左右する瞬間には、営業担当者はほとんど同席していません。企業幹部が自社の問題や優先順位について議論して決定を下すのは、通常、営業担当者との打合せの場ではなく社内会議の場です。(中略)
有能な営業担当者は、顧客に対して(To)営業するわけではありません。彼らと共に(With)営業するのです。
彼らは顧客の問題に対する考え方に影響を与えます。顧客が明確で説得力のある物語を語れるようにし、チームが次に何をすべきかについて足並みを揃えます。しかし、それでも営業担当者が取引をまとめるわけではありません。取引をまとめるのは顧客自身です。(中略)それでは、営業担当者の仕事とは何でしょうか。それは顧客を支援することです。顧客が現状(問題)から望む状態(成果)へ移行できるように手助けすることです。
この本でも、協業取組タイプのアプローチで顧客の購買プロセスを後押しすることがキーメッセージとなっています。
協業取組タイプその3:顧客の意思決定/合意形成を直接支援する「購買プロセスファシリテーション」
そして最近登場したのが「購買プロセスファシリテーション」という営業の新しい役割。それがどのようなものなのか、見ていきましょう。
購買プロセスファシリテーションとは、顧客の購買プロセスの各段階における意思決定を支援するツールを作成・提供すること。そして、これまでのように製品の特徴を押し付けるのではなく、それぞれの顧客特有の意思決定の難所について深く理解してそれを顧客と共に解決するのです。
特に面白いと思うのは、「顧客にとって有用な知見(インサイト)の提供」を、購買プロセスファシリテーションを実現するための手段の1つだとしているところ。顧客の購買プロセスを可視化してその進捗を一緒にレビューしたり、顧客関係者が集まれるようなTeams等のスペースを用意したりするのと同列に、インサイトの提供を位置付けているのです。
顧客中心型営業で求められる役割が「インサイト提供タイプ」から「協業取組タイプ」へと拡大傾向
ここまで顧客中心営業というコンセプトの登場から2025年3月現在までの進化の流れを概観してきました。そこで1つ言えるのは、顧客中心営業の時代に求められるコンサルティング的な機能は、専門知識やインサイトの提供だけでは済まなくなってきているということ。それらの情報をもってしても、なかなか順調に購買プロセスを進められない顧客に対しては、ときにコラボレーションし、ときに顧客のキーパーソンとタッグを組んで、そしてときに顧客の関係者を集めて自らファシリテーターとしての役割を果たしながら、顧客の購買を後押ししてあげる必要があるのです。
では協業取組タイプの顧客中心型営業として、まず何をすればよいのでしょうか。
最初におススメするのが、顧客と一緒に購買プロセスを可視化していくこと。多くの関係者や社内承認を経なければならない購買プロセスは、顧客にとっても複雑なもの。それを可視化し、顧客だけでは乗り越えるのが難しい難所を特定し、そこを乗り越えるための支援方法について考えるのです。具体的な内容は「営業の新しい役割『購買プロセスのファシリテーション』とは」に記載していますので、ぜひ参考にしてください。
そして購買プロセスを可視化・共有できたら、顧客が社内を説得・合意形成するために大事な資料である起案書/稟議書/計画書を作成します。ここで大事なポイントは、外部にいる売り手が作る提案書ではなく、顧客自身が作る社内決裁用の資料を顧客と一緒に作るということ。このためには顧客とのコラボレーションや関係者を集めてのファシリテーションが不可欠。こちらについては「顧客の意思決定を支援!『Selling With』に学ぶ提案書の新常識」にトライツとしてどのように取り組んでいるかも含めて解説していますので、ぜひお読みください。
これからも「顧客中心型営業」の最新動向を継続調査・報告していきます
顧客中心営業という言葉が話題になり始めてから5年余り。この間に顧客の購買プロセスを後押しするために営業に求められる機能が大きく変化/進化してきました。そして今後はさらに大きな変化が起きる可能性もあります。トライツブログでは顧客中心営業という大きなパラダイムシフトをこれからも引き続き調査し、今回のように整理してお伝えしていきます。続報もぜひご期待ください。