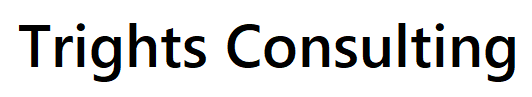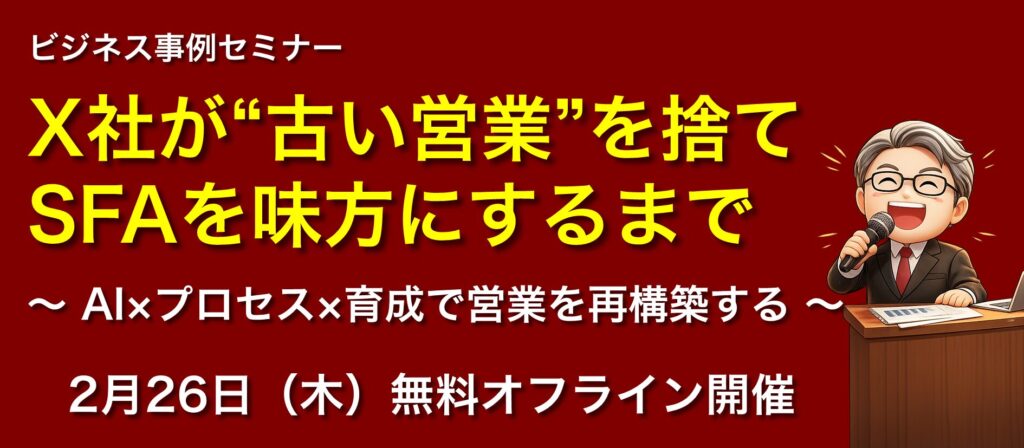この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。
「入社時の研修は充実していたけれど、その後は自己流でなんとかしている……」
こんな悩みを抱える営業担当者は少なくありません。日本の多くの企業では、新入社員や異動で新たに配属された社員向けの実務研修(オンボーディング)に力を入れていますが、その後は「現場で覚える」というスタイルが根強く残っています。
しかし、変化の激しい現代のビジネス環境ではこれでは不十分。生成AIなどの新しいテクノロジーが次々に登場し、顧客のニーズや顧客の購買行動も変化・多様化する中で、一回限りではなく継続的な学習が求められるようになっています。この課題を解決するキーワードが、「エバーボーディング」です。これは「継続的な学習を通じて、従業員の成長を支える組織文化」を指し、売上向上に直結する重要な考え方として注目されて始めています。
今回はこの「エバーボーディング」という考え方とその背景、私たちの業務への取り入れ方について考えてみたいと思います。学び続け、進化し続ける営業組織になるためのヒントを一緒に探っていきましょう。
なぜ「継続学習」が売上を伸ばすのか?
今回ご紹介するのは、「How to Build a Learning Culture That Drives Sales Success」(営業の成功を加速する学習組織の築き方)というブログ記事。これは、セールスイネーブルメント・ソリューションを開発・販売しているAllego社が、調査会社Rain Group社と共同で実施した調査レポート『The Impact of Continuous Learning on Sales Performance』(継続学習が営業パフォーマンスに及ぼす影響)を簡潔に整理し直したものです。
この調査レポートが営業の継続学習を必須だと捉えている根拠は、業績に直結するからです。
Allego社およびRAIN Group社の調査によると、継続学習を取り入れた組織では営業担当者が早期に営業の最前線で一人立ちできるようになるため、組織全体の業績達成率がそうでない組織と比較して4.9倍高くなっています。また、そのような組織では、営業リーダーによって強く推進されるため、継続学習が継続・定着する割合が 2.2 倍高くなっています。
このデータが示しているのは、「学習は一度きりではなく、継続的に行うことでより高い成果が出る」ということです。スポーツ選手が日々のトレーニングを欠かさないように、営業担当者も最新の知識やスキルを磨き続ける必要があるということなのです。
特にB2B営業では、新商品の発売や競合企業の動向、そしてWebやAIを活用した顧客の購買行動などの日々起きている変化に柔軟に対応しなければなりません。このためには、最初のオンボーディングだけでなく継続的な学習を日常の業務に組み込む「エバーボーディング」が不可欠なのです。
「継続学習」できる組織を作る6ステップ
それでは、どうやって継続学習「エバーボーディング」できる組織を作ればいいのでしょうか。記事では以下の6つのステップに沿って進めることが大事だと述べています。
ステップ1:リーダーから賛同を得る
リーダーは継続学習というコンセプトを応援するだけでなく、積極的に研修に参加したり、自らが得た教訓を共有するなどして学習に自分自身の時間と労力を投資しなければなりません。ステップ2:学習を日常の業務に組み込む
営業担当者が求めているタイミングで、適切な研修や資料を提供します。研修が単なるタスクやイベントではなく、営業担当者の日々の業務を支援するリソースだと思ってもらうのです。ステップ3:学習の進め方を個人に合わせる
営業スキルを評価してギャップを特定し、各営業担当者に合わせた学習プランを作成します。ステップ4:共同作業とナレッジ共有を促進する
学習文化はメンバー全員の共同作業によって育まれます。営業担当者に経験から得たノウハウや成功事例、教訓を共有するように促します。また、貴重なコンテンツやナレッジを提供してくれた担当者には報酬を与えます。ステップ5:学習を測定し最適化する
営業トレーニングプログラムの活用状況と業績を分析し、何が上手くいっていて、何がそうではないのかをチェックして、改善すべき領域を特定します。ステップ6:学習に対して報いる
学習を通じて成長した担当者や、チームに貢献した担当者を称えます。これによって組織における学習の価値を強化します。
確かに6つのステップのどの要素が欠けても、継続学習が文化として営業組織に根付くことはないでしょう。その意味で、網羅性の高いリストになっていると思います。
この6つのステップのうち、日本の営業組織として最初にぶつかるハードルは2つめの「学習を日常の業務に組み込む」ではないでしょうか。どうしても普段の営業業務と研修などの学習は別モノだとなってしまいがちですし、これまでに自分がそのような体験をしていないと、どんな学習体験を提供したらよいかわからないものです。
「ステップ2:学習を日常の業務に組み込む」を実現するアイデア
そこで、ここから先は私が個人的に今までのキャリアの中で経験したことや、クライアント企業で実践されていた取組を抜粋してご紹介します。
アイデア1:「週1回、朝10分」のインプットとアウトプットの場を作る
私が新入社員で入ったコンサルティング会社では、社長直轄の新規事業開発系の部署に配属されました。そこで毎日、今朝の新聞記事の中で何が面白いと思ったのか、それによって自分やクライアントのビジネスにどんな影響があるのかを社長にプレゼンし、ツッコミや分析の切り口を指導してもらうということを経験していました。
さすがに毎日、営業の全員に対してこれをするのは難しいと思います。その代わりに例えば毎週の営業会議の中で、業界の最新ニュースや製品のアップデートをチェックしたり、顧客の声を共有したりする時間をもってみてはいかがでしょう。
アイデア2:「成功のパターン」を言語化する
上手くいった商談を会議で報告する際に、金額や売上の時期だけでなく、「なぜ成功したか?」「どこが分岐点だったのか」「他の商談にも活かせるノウハウが何か」を具体的に深掘りすることを習慣化するのもおススメです。
アイデア3:組織全員での「学びの場」を用意する
クライアント企業の1社では、四半期ごとに事業部内の全メンバーを集めて戦略共有会議を実施しています。午後1時から2時までは事業部長や営業企画部長による戦略や計画を共有する時間。そして2時以降は、メンバーが持ち回りでナレッジ共有のためのイベントを企画・運営していました。顧客の声をかき集めて事業として対応するものを決めたり、期間内に作られた提案書を集めて見比べるといったものです。担当となったメンバーには一時的に負荷が発生しますが、四半期や半期ごとであれば恒例のイベントとして十分に楽しく運用可能だと思います。
毎週のこのブログもトライツにとって大事な学びの時間
そしてこのブログ自体も、トライツとしては大事な学びの場となっています。海外含めて最新のB2B営業やマーケティングにどのような動きがあるのか、それにどのような意味があって日本の営業組織においてどのような示唆があるのか。日々のプロジェクトから少し頭を離して、最新のトレンドやコンセプトについて考える貴重な時間となっています。メールマガジンなどでこれをお読みの皆さんにとっても、学びの時間となっていれば嬉しく思います。
学習は「コスト」ではなく「投資」
変化の速い現代では、学びを止めた組織は顧客から選ばれなくなるという現実があります。海外の営業本でよく使われるセリフとして「あなたがあなた自身に投資していないのに、なぜ顧客があなたに投資するのか?」というものもあるほど。その一方で、継続的な学習文化を築くことで、営業チームの成長が加速し中長期的な売上向上につながることが十分に期待できると思います。
「エバーボーディング」は特別な仕組みではありません。まずは「小さな学びの積み重ね」から始めてみてはいかがでしょうか? その一歩が、あなたのチームを「ずっと学び成長し続ける組織」に変える第一歩になるはずです。
参考:「How to Build a Learning Culture That Drives Sales Success」(Michelle Davidson, Allego, January 25, 2025)