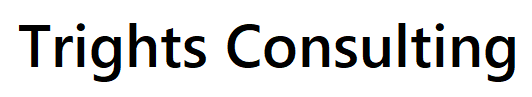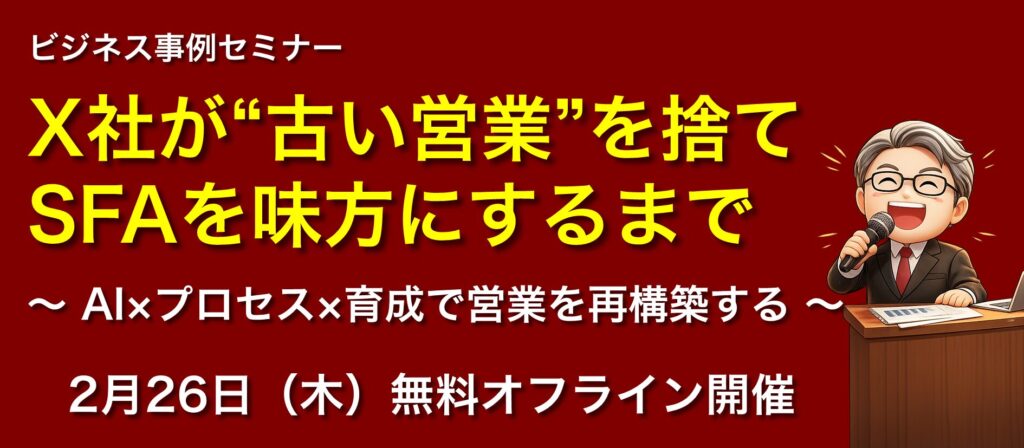この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。
営業についての気の利いたフレーズの1つに「人は感情で購買し、論理で正当化する」というものがあります。私たちが消費者として旅行先を決めるときも、家を選ぶときも、「これがいい!」という感情が先行してから、それを自分に納得させたり人に説明したりする際に論理を使う、ということがよくあります。
現在のB2Bでの購買はRFP(提案依頼書)で評価基準が明示されたり、起案書や稟議書を作成したりと論理的な説明が大事にされています。とはいえ、担当者が「これを欲しい」「この会社に仕事を任せたい」と思う場面では、多分に感情や心理的な要素が働いています。私事ですが、つい最近も「一緒に仕事をしたい」と連絡をくれた人とその思いを一緒に紐解くことで、RFPの評価基準を一緒に言語化して表にまとめた、ということもありました。
このようにB2B営業においても大事な「顧客の心理/感情」ですが、これについての記事や調査データはあまり多く世の中に出回っていません。そんな中、とても興味深い記事を発見しましたので、今回ご紹介します。顧客の心理/感情がどのように私たちの商談に影響を与えているのか。そしてそれを望ましい方向に軌道修正するためにどうすればよいのか。一緒に見ていきましょう。
B2B営業の最大の障壁は顧客の脳内で引き起こされる「自動思考」にある?!
今回ご紹介するのは、オーストラリアで心理学的な知見を使ってビジネスの課題解決を行っているコンサルティング企業の、ピープル・プラス・サイエンス社の記事「How to Hack the Limbic Brain for B2B Sales Success」(B2B営業を成功に導く大脳辺縁系の活用法)。同社は「科学と調査研究は、問題の根本原因を捉えた解決策を提供できる」を基本ポリシーとしているちょっと変わった企業です。
同社が考えているB2B営業における心理的/感情的な問題は、以下のようなものです。
あなたが用意したパンフレットも、ケーススタディも、提案書もすべて完璧です。なのに、なぜテーブルの向こうにいる顧客は依然として懐疑的な表情をしているのでしょうか?あなたは顧客の脳のうち論理を司る前頭前皮質に壮大な傑作を提示しましたが、感情を司る大脳辺縁系での戦いに負けてしまったのです。
B2B営業における最大の障壁は論理的なものではなく、心理的なものです。顧客の自動思考が、脳の大脳辺縁系に恐怖反応を引き起こし、取引の成立を阻害してしまうのです。
専門用語ばかりで少し難解ですが、中身を紐解いていきましょう。
顧客の自動思考が生み出す「時間稼ぎ」「過剰なこだわり」「不適切な意思決定」
まずは、「自動思考」という心理用語について解説します。自動思考とは、これまでの経験や認知のパターン、ものの考え方に由来して、意図せずに相手や出来事に対して抱いてしまう印象や感情のこと。商談の場では、営業の話を聞きながら顧客の頭の中で様々な自動思考が巡っています。
「誤字/計算ミスがあったから、この提案書全体が信用できない。不完全だ」
「以前も同じようなテーマに取り組んだことがあったようだが、失敗したと聞いている。これもきっと失敗するはず」
「ケーススタディもどうせ『盛って』書いてあるんでしょう。実際は違うんじゃないの」
「こんな高額な見積を上司に見せても、取り合ってくれるどころか怒られるだけだろう」
「手厚いサポートと言っているけど、どうせ売ったらそれっきりなんでしょ」
「失敗したら責任を取らされて、将来のキャリアに傷がつくに違いない」
これらは決して論理的なものではないのですが、このような自動思考が始まってしまうとなかなか商談が前向きに進まなくなってしまいます。意思決定の時間稼ぎをしようとしたり、「価格」や「納期」など顧客の恐怖の原因となっているものに過剰にこだわったり、機能が足りないものの安価な他社商品に決めたりしてしまいます。
顧客の自動思考を未然に防ぐ「MICARES」モデル
このような顧客の自動思考の発生の仕方を理解し、それが起きないように未然に防がなければならない、というのが記事のメインメッセージ。その具体的な方法として提唱しているのが、「MICARES」というモデルです。
動機(Motivation):顧客が何に動機づけられているかを明らかにしましょう。
重要性とステータス(Importance & Status): 顧客が自分のことを良く思えるような言葉を使いましょう。
確実性(Certainty): 具体的なプロセスの明示と、成果を保証することで、脳にかかる神経的な負担を抑えます。
自律性(Autonomy): 案を押し付けるのではなく、顧客が主導権を握っていると感じられるよう、選択肢を提示しましょう。
信頼関係(Relationship & Trust):信頼関係を築くことで、顧客に寛大さが芽生えます。
公平・公正(Equity & Fairness): 価格設定や取引条件が透明かつ公正であることを理解してもらいましょう。
共通の価値観(Shared Values): 商談相手の個人的な価値観と顧客企業の目的・戦略とを結び付けます。
7項目もあるため、顧客の心理/感情を理解し自動思考を起こさせない工夫がいっぱいの、網羅性の高いリストになっていると思います。
実際に商談の相談を受けてきた経験から、私がこのMICARESの中でも特に大事だと思っているのが「確実性」と「自律性」、そして「信頼関係」です。プランや成果物など顧客が気にしているであろうことについて、できるだけ具体的に示し、まだ不確実な要素があれば「どのステップでどう具体化できるか」を補足する。お勧めの案を示しはするものの、顧客自身が選べるように複数の案を提示する。そして、このようなやり取りを丁寧に行うことで、顧客から「自分の悩みや不安の解消のために寄り添ってくれる人だ」と思ってもらえる信頼関係を構築する。この3つの要素をぜひ商談の中で活用してみてください。
生身の人間である顧客の心理/感情に寄り添うのがB2B営業
最後に、B2B営業において顧客の心理/感情を意識することの重要性について雄弁に語っている、記事の締めのメッセージを引用します。
最も成功しているB2B営業担当者は、応用心理学者そのものです。顧客からの反対意見は、顧客が抱いている恐怖や不確実性、地位や安全への欲求といった、より深い心理的反応が表面的に現れたに過ぎない、ということを彼らはよく理解しています。
心理学の原則を活用して顧客の思考パターンを再構築することで、単なる売り込みから脱却し、人間の脳の言語、つまり感情についての言語を操る信頼できるアドバイザーへと成長できるのです。
私たちが顧客の前では緊張し不安になってしまう生身の人間であるように、顧客も不確実性や不安、恐怖心に駆られることもある生身の人間です。「論理的におかしい」「筋が通らない」反応を意図せずにしてしまうこともあります。今回の記事が、そんな顧客に寄り添うための一つのヒントとなれば嬉しく思います。
参考:「How to Hack the Limbic Brain for B2B Sales Success」(People Plus Science, September 15, 2025)