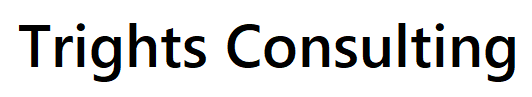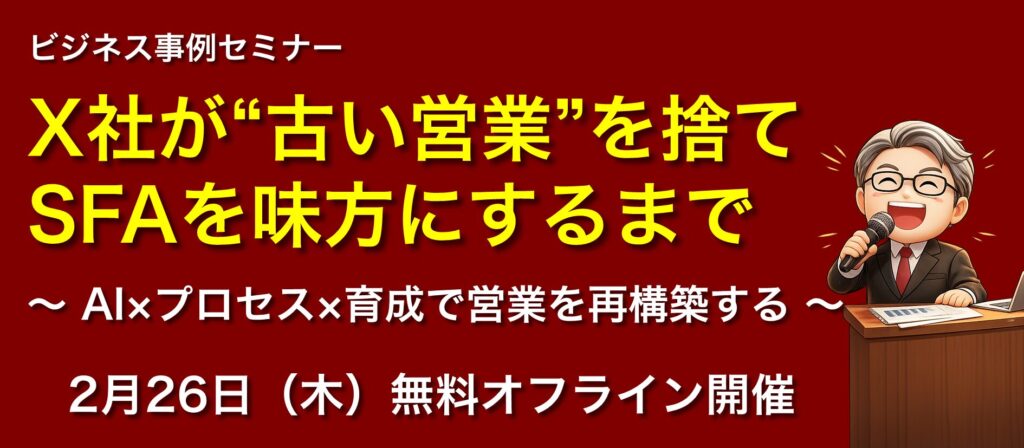この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。
顧客がWebやAIを使って必要な情報を集められるようになっている現在では、営業に求められる役割が大きく変化しています。これまでもトライツではブログやセミナーを通じて、顧客が購買の主導権を握っている現在の営業のあり方として「顧客中心営業(Customer-centric Sales)」や「コンサルティング営業」というキーワードで、顧客の購買活動を支援する新しい営業の役割をご紹介してきました。
そんな中、これまでにご紹介したものとは違った新しい角度で新時代の営業の役割定義しよう、という面白い試みをしている企業を見つけました。その企業が提唱する新時代の営業の役割は「購買プロセスのファシリテーター」。これが一体どのようなものなのか、これまでとは何が異なるのか、そして私たちの普段の営業活動にどのように取り入れられるのか、一緒に学んでいきましょう。
顧客の複雑で難解な購買プロセスを進めるには、ファシリテーターが必要だ
今回ご紹介するのは、英国ロンドンに拠点を置く営業コンサルティング会社Shift90の共同設立者、マーク・ギブソン氏の記事「The Shift – From Selling to Buyer Facilitation and a New Era in Sales」(ザ・シフト – 販売から購買促進へ – B2B営業の新時代)。これは近日中に発売される同名の著書の抜粋でもあります。記事の中で営業に求められる役割が、これまでの自社商品の特徴を押し付ける販売から、顧客の複雑で難解な購買プロセスをファシリテーションすることへとシフト(転換)する必要がある、と述べています。
まずは、このシフトが必要な背景を手短におさらいしておきましょう。
今日のB2B購買の状況は根本的に変化しています。意思決定チームの平均的な規模は6~11人に増え、一般的な購買期間では12~18ヶ月間に伸び、その間に15~20回以上の社内会議が必要となっています。調査によると、意思決定チームの機能不全により購買活動の40~60%が購入に至らず、顧客および売り手企業のビジネスに直接的な悪影響が及んでいます。
この「顧客の購買プロセスが複雑化・長期化しており、かなりの割合の購買活動が意思決定に至らない」という問題については、以前のトライツブログの記事「海外で話題の営業本『ジョルト・エフェクト』から学ぶ!優柔不断な顧客を支援する『4つの処方箋』」でも取り上げました。また、その解決のためのヒントとして「『売り込む』時代はもうおしまい!顧客と『共に売る(Selling With)』とはどういうことか」では、共に売る(Selling With)という観点で顧客の購買のキーパーソンを支援する方法もご紹介しています。
購買プロセスファシリテーションとは、購買を顧客任せにしないこと
このような購買プロセスを自力ではなかなか進められない顧客に対する、営業としての支援の仕方としてギブソン氏が提唱しているのが「購買プロセスファシリテーション」です。ではこれがどのようなものなのか、記事を見てみましょう。
購買プロセスファシリテーションとは、顧客の購買プロセスの各段階における意思決定を支援するツールを作成・提供すること。そして、これまでのように製品の特徴を押し付けるのではなく、それぞれの顧客特有の意思決定の難所について深く理解してそれを顧客と共に解決するのです。
これを一言で言うならば、「購買プロセスを顧客任せにしない」ということだと思います。これまでのように製品の特徴や価格といった情報を提供するだけでその検討を顧客任せにするのではなく、顧客社内での議論や意思決定が円滑に進むようにサポートすることで、購買の意思決定に至らない「優柔不断」の状態に陥るのを防ごうということです。
購買プロセスを停滞させないために有効な支援方法とは
それでは、具体的にどんな支援が有効なのか、記事から抜粋したのがこちらです。
顧客との協働スペースの準備
・すべての関係者が利用できる単一のデジタルワークスペース(Teamsなどのプラットフォーム)
・関連資料やコミュニケーションを集中管理顧客にとって有用なインサイト(知見)の提供
・ビジネスケース(訳注:課題と背景、解決策案の評価選定、目指す成果指標とスケジュールを整理したもの)
・ROIシミュレーション
・リスク分析・評価のフレームワーク顧客の購買プロセスの可視化
・購買プロセスを管理可能な段階に分割し、各プロセスの終了基準と目標終了期日、責任者/部署などを明確に定義測定可能な導入成果の設定
購買プロセスファシリテーションの要素がすべて網羅できているとは言い切れなさそうですが、購買プロセスが停滞してしまいがちな難所を上手く進めるのに有効な支援例として参考になるのではないでしょうか。
記事の中ではこの「購買プロセスファシリテーション」という役割/機能を取り入れることによって、顧客の購買にかかる期間を最大で30%短縮でき、自社の受注に至る割合が50%も向上すると訴えています。確かに、このようなことができれば競合企業とはまったく異なる立場/関係性で顧客と接することができます。しかし、従来の販売アプローチからこのやり方へとシフトしようとすると、2つの大きなハードルが待ち構えています。
購買プロセスファシリテーション化への課題①「顧客の期待役割を変える」
1つめのハードルは、どうやってこの新しい「購買プロセスファシリテーション」という立場を手に入れるのか、ということ。これまで自社商品の売込しかしてこなかった営業担当者のことを、顧客が急に「自分たちの購買プロセスの推進支援をしてくれる人だ」と思うようにはなりません。「これまでとは違った関わり方で顧客の購買活動をサポートしたい」と言うことが伝わるような、期待役割を転換するための働きかけ、これまでセミナーやブログでご紹介してきた「インスパイア・プレゼン」が必要です。
購買プロセスファシリテーション化への課題②「部分的な経験を積み重ねて信頼を勝ち得る」
そして2つめのハードルは、インスパイア・プレゼンが成功したとしても顧客の購買活動全般を任せられるファシリテーターになるのは困難だ、ということです。どれだけ自分たちのことを思ってくれて、役に立つ情報を提供してくれたとしても、顧客がすべてのファシリテーションを任せてくれることはあり得ません。そのため、普段の社内プロジェクトのファシリテーターのような全体をコントロールする立場を目指すのではなく、顧客との打合せの場をミニ・ワークショップだと捉えて、部分的にファシリテーションを行うのが現実的です。
その中でも特に有効なのが、ギブソン氏も記事の中で触れていた「顧客の購買プロセスの可視化」だと思います。どういうステップを踏む必要があるのか、各ステップをクリアするために何が必要なのか、これまでの類似案件ではどこで購買活動が停滞してしまったのかについて顧客の購買関係者と意識合わせをしておくことで、作るべきビジネスケース/提案資料の内容もより具体化することができます。トライツのクライアント企業でも、これに取り組んだことでその後の顧客の社内会議にアドバイザーとして呼ばれることが増え、結果として大型案件の受注につながったという事例もあります。
このように、部分的にファシリテーションの経験を踏んでいくことによって、少しずつ顧客からの信頼を勝ち得ていく、というのが現実的な「購買プロセスファシリテーション」へのシフトの方法だと思います。
皆さんの顧客は購買プロセスのファシリテーターを必要としていませんか?
今回ご紹介した「購買プロセスファシリテーション」という考え方は、顧客が購買の主導権を握る現在において、営業担当者が担うべき役割/機能をこれまでなかった角度から具体化しようという、面白い試みだと思います。これまでのコンサルティング営業などでは表現しきれなかった部分、特に購買プロセスの全体像の可視化/共有や、顧客関係者のコミュニケーションやドキュメント管理を一元化するスペースづくりなどは、参考になるのではないでしょうか。
皆さんの商談で、こちらとして必要な対応はしてきたのに、顧客が決め切らなかったために止まってしまったものの中には、購買プロセスを進めるためのファシリテーターを必要としていたものがあったかもしれません。今回ご紹介した支援方法の何があればうまくいっていたのか、そして今進めている商談をさらに加速させるためにどれが有効そうなのか、今後に向けて考えるヒントにしてみてください。
参考:「The Shift – From Selling to Buyer Facilitation and a New Era in Sales」(Mark Gibson, Shift90, January 22, 2025)