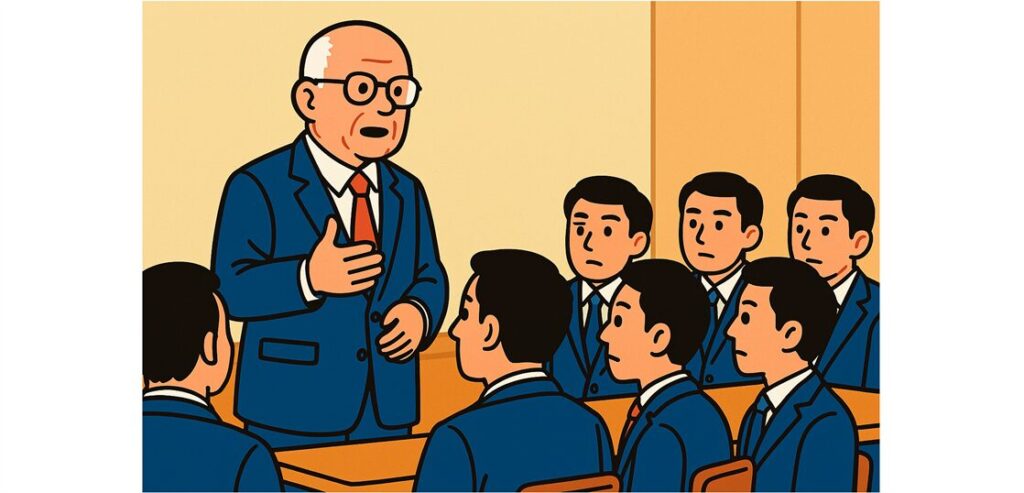この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。
私は日々、営業のコンサルタントとして営業プロセスやツールを設計したり、その内容を体得してもらうための研修や現場支援をしていますが、時には研究部門の方と一緒に、ヒト試験のプロセスの全体像を可視化し、それを改善し、さらに進捗管理できるツールの開発をするなどという仕事に携わることもあります。
そのため定期的に業務プロセス改善/管理系の本を読んだりして、自分の知識をアップデートするようにしています。つい最近改めて読み返した本の中に、営業でも参考になりそうなアイデアが多数含まれていましたので、ぜひご紹介したいと思います。その本とは日経BPクラシックスの『危機からの脱出』。これは品質管理分野の巨人エドワーズ・デミング博士が1982年に出版した、品質管理および業務改善の古典ともいえる名著。営業とは一見関係なさそうなのですが、営業企画や営業のマネージャーの方に学んでいただきたい名言が溢れています。
そこで今回はデミング博士の名著をもとに、営業プロセスの管理・改善について学んでいきたいと思います。SFAの展開とともに、商談の進め方がプロセス化されるようになり、さらにそれを支える研修やツールといった仕組みが揃ってきている現代の営業。プロセスを管理・改善する方法について、一緒に古典から学びましょう。
日本の高度成長期を下支えしたデミング博士とその名著『危機からの脱出』
本の中身に入る前にデミング博士についてもう少し解説させてください。博士は戦後間もないGHQ占領下の日本に訪れ、日本の経営者や技術者に対して精力的に品質管理やプロセス改善の講演を行ったことで有名。その後日本の自動車業や電機業の各企業が博士の講演内容を取り入れて、「安かろう悪かろう」だった日本の製品が「ジャパンアズナンバーワン」と呼ばれるまでに進化したため、日本の高度成長期の陰の功労者として知られています。
そんなデミング博士が1950年前後に日本で行った講演、そしてアメリカに帰ってからフォードなどの米国企業に行ったコンサルティングで得た知見をまとめたのが、今回ご紹介する『危機からの脱出』。その中でも、特に営業に役立つ部分を抜粋してご紹介します。
名言①「新鋭設備やツールや素敵なアイデアによる効果は小さい」
まずは、「最新のテクノロジーや設備さえ導入すれば、生産性が向上するに違いない」という迷信に対して、博士はスパッと切り捨てています。
オフィスや工場の自動化機器や自動記録装置も解にはならない。そのような先進的機器を呼び物とした展示会には何千もの人が詰めかけ、生産性の立ち遅れを簡単に取り戻す方法を見つけようとする。できるだけハードウェアに頼りたいのだ。(中略)だが、新鋭設備やツールや素敵なアイデアの複合効果は相対的には小さい。この生産性の立ち遅れを克服するのはマネジメントの責務だ。ハードウェアやツールの導入で得られる効果は、マネジメントによって達成される大きな生産性向上には及ぶべくもない。
営業の世界においても、「SFAやAIといった最新のツールを入れさえすれば、DXが実現されて生産性が高まるに違いない」という思いで、営業プロセスが定義やブラッシュアップされていない状態にも関わらず、テクノロジーだけが外付けされてしまう、ということがよくあります。そうではなく、「マネジメントによって達成される大きな生産性向上」、すなわち業務プロセスを明確に定義し、指標を測定・分析して改善につなげるという基本を徹底することの重要性を、博士は述べています。
名言②「分析のためにはデータが統計的に管理されたものでない限り、何の役にも立たない」
それでは、本来の生産性向上を実現すべく、指標を測定・分析しようとする人にも博士は警鐘を鳴らしています。
分析の目的のためには、当該データが統計的に管理された状態から得られたものでない限り、その分布や、計算(平均値、最頻値、標準偏差、カイ二乗、t検定など)は、プロセスを良くする上で何の役にも立たない。
途中で統計学の用語がたくさん出てきますが、言わんとしていることは明確です。営業の場合はSFAなどに蓄積されたデータを使って分析するのですが、そのデータが「統計的に管理」、すなわち正しく観察・入力されたものになっていないと分析した結果に意味がありません。
例えば、「どのような状態になったら商談化できたと言えるか」の基準が明確になっていなかったり、BANTCなどの顧客情報が十分にそろっていなかったり、そしてそもそも顧客が自社商品や購買活動そのものに前向きなのかが正しく評価されていなかったりというように、SFAなどに入力されるデータの質がバラバラになっていることが多くあります。そのため、営業プロセスや用語を明確に定義する、報告してほしい情報は入力欄を作るなど定型化する、顧客や商談を適切に評価するための物差し/規準を組織で共有する、といった営業管理の型化が不可欠なのです。
名言③「『システム』を良くする実質的な改善こそがマネジメント/リーダーの仕事/責任だ」
そして、博士は業務のシステム/しくみを整備し、改善するのがマネジメント/リーダーの大事な仕事だと繰り返し主張しています。
実質的な改善というものは、それが何であれ、「システム」そのものに変化を起こすことからのみ生じ得るということだ。「システム」を変えるのは、マネジメントの責任である。
パフォーマンスについての数字を、「システム」の中にいるグループの人々をランク付けするために使ってはならない。むしろ、リーダーが「システム」そのものを良くするのを助けるために使うべきだ。
ここでいう「システム」とは、営業で言うところの営業プロセスや研修、ITツールや商品紹介資料などのしくみ/施策のこと。デミング博士は特に製造業でのプロセス改善が専門ですので、目標を達成できない場合に特定の個人にその責任を求めるのではなく、そのような成果を生み出しているシステム側にまずメスを入れるべき、というのが基本的な考え方です。
また後段の「パフォーマンスの数字は、人のランク付けではなくシステムの改善のために使われるべき」という考え方は、セールスイネーブルメントつまり「営業活動を段階・プロセスごとに分解し、それぞれの段階・プロセスで使われるコンテンツやツール/システム、関連する研修などの各種施策を評価・改善して全体の生産性を高める取組」にも通じるものがあります。デミング博士が40年以上前に本の中で書いたこと、さらに遡ると60年以上前に日本の経営者や技術者向けに語ったことは、現在の営業においてもまったく古ぼけていないものだということがよくわかる部分だと思います。
営業がアートからサイエンスに転換したことで、デミング博士の考えが営業にも適用できるようになった
以前のB2B営業は、個人の才能や人柄に強く依存したアート/芸術のようなものとして捉えられていました。それが、営業を詳しく解明していこうという2000年ごろからの動きによって、明確なプロセスに則ったサイエンス/科学として捉えられるのが一般的になってきました。
このアートからサイエンスへの転換が起きたことによって、デミング博士の名言の数々が現在のB2B営業にも当てはまる、価値のあるアドバイスになったのだと思うのです。
「学びへの意欲」と「職務への献身」:デミング博士からの40年越しのエールを受け取ろう
最後に、デミング博士が高度成長期に向かっていく日本の産業界を間近で観察していた様子をご紹介します。
1950年は新たな品質立国・日本の始まりだったのだ。この年私は、日本製品は5年以内に世界市場に攻め込み、日本の生活水準はやがて先進諸国と同じ水準まで上昇するだろうと予測した。この予測には自信があった。根拠は次の通り。
①日本の労働者を観察して得た見解
②日本のマネジメント層の人々の知識と、自身の職務への献身、学びへの非常に強い意欲
③日本のマネジメントは必ずや自身の責務を引き受け、実行していくに違いないという信頼(後略)
博士の教え子のような存在であった日本の産業界に対して、温かい称賛のまなざしを送っていたことがよくわかる文章です。「職務への献身」や「学びへの非常に強い意欲」など、今の日本では皮肉になりかねないものもあります。しかし、ここは前向きに、積極的に学習を重ねて業務プロセスの改善を進めていけば、営業においても生産性の向上が実現できるという、博士からの40年越しのエールだとも捉えるべきではないでしょうか。
参考:「危機からの脱出 Ⅰ・Ⅱ 日経BPクラシックス」(著:W・エドワーズ・デミング, 訳:成沢俊子、漆嶋稔、日経BP、2022)