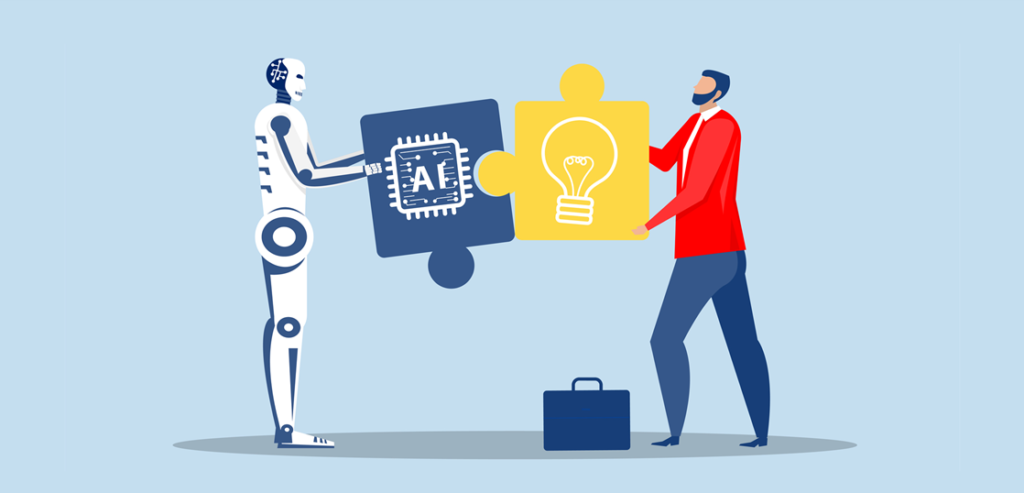この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。
AIの発達によって、今まで人間が行っていた様々なことに対する「不要論」がSNSなどで話題になっています。代表的なものを挙げると、リアルタイム翻訳機能による「英語学習不要論」。AIがプログラムを書くようになったことによる「プログラミング/コーディング不要論」。そして、営業分野でもAIに営業職が代替される「営業不要論」という話も出ています。
この営業不要論については、以前の記事「『セールスマンの死』は本当に訪れるのか?AI時代に求められる営業の能力とは」でも取り上げています。ざっくりと要約すると、B2B営業にはAIでできる入門レベルの業務と、そうでないより高度な業務とがあり、入門レベルの業務はAIに任せて生身の人間はより高度で顧客と直接会話する業務にシフトすべき、という内容です。B2B営業の業務のレベル差によって、AIと生身の営業担当者とで分業しようというお話でした。
そのような中、業務レベルではなく「顧客側の要望という観点からも、生身の営業担当者の必要性が今後高まる」という内容のレポートが最近発表されました。AIが様々な情報を瞬時に教えてくれるようになっている現代において、顧客は生身の営業担当者にどのようなことを期待しているのか、一緒に見ていきましょう。
最新レポート「2030年のB2B営業に影響を与える重要トレンド」を読み解く
今回ご紹介するレポートは、世界有数のB2B営業関連の調査会社Gartner社の最新レポート「Top Trends for CSOs Impacting B2B Sales in 2030」(営業トップが知っておくべき2030年のB2B営業に影響を与える重要トレンド)。このレポートで一番の目玉となっているのがこちらの予測です。
AIを活用したソリューションは、特に営業プロセスの初期段階において、スピードや効率性、そして顧客にとっての利便性を提供しています。しかし最近の分析によると、顧客は生身の営業担当者との関わりを依然として求めています。2030年までに、B2B購買担当者の75%がAIよりも生身の人間との関わりによる購買体験を求めるようになると予測しています。
このレポートを読むにあたって大前提として押さえておきたいのは、単純なAI不要論ではないということ。営業プロセスの初期段階、コールドメールやSNS掲載用のコンテンツ作成、新規顧客からの問合せへの回答といった、定型化可能な業務のAI化を否定するものではありません。
技術進化によって登場した「AIの不気味の谷」
それではなぜ購買担当者がAIよりも生身の営業担当者とのコンタクトを好むようになるのか、レポートの続きを見ていきましょう。
「不気味の谷」とは、人間によく似ているものの、真の本物らしさには程遠い存在と接する際に、人が感じる不安感を指します。(中略)
購買担当者はAIを活用したツールの効率性と利便性、特に情報収集や購買プロセスの初期段階でのガイダンス機能を高く評価することでしょう。しかし、購買プロセスが先に進むにつれて、AIの限界が明らかになります。人間同士のやり取りの特徴である、真の共感、繊細な理解、微妙なニュアンスといったものの欠如は、購買担当者に不快感や不信感を生み出します。
その結果、購買担当者は生身の人間ならではの安心感と個別対応を、営業担当者に求めるようになるでしょう。この傾向はすでに顕在化しており、多くの購買担当者が重要な意思決定の局面において人間の介入を希望しています。
「不気味の谷」で有名なのは、大阪大学の石黒教授が作成した教授本人そっくりのロボットでしょう。まるで人間のように見えるのに、振る舞いやニュアンスが微妙に人間らしくないと、私たちは不気味さ、気持ちの悪さ、不安感を感じるもの。AIが高度に進化しているからこそ、この「不気味の谷」がB2Bの購買体験においても発生するというのです。
複雑で高額な商品の購買ほど、顧客は生身の人間との対話を求めている
レポートではさらに、どのような購買において生身の営業担当者が求められるようになるかについて記述しています。
ここ数年、Webページ等でのセルフサービスやAIを活用した購買体験への関心が高まってきましたが、現在ではその傾向は逆転し始めています。特に複雑なソリューションや高額商品の購買においては、生身の人間との対話を求める購買担当者が増えています。
この生身の営業担当者による支援が必要になる購買パターンですが、記事の中にある「複雑なソリューション」や「高額商品」以外にも、「顧客の状況に応じたカスタマイズが必要」「顧客が始めて購入するため顧客社内の意思決定のサポートが必要」「専門家によるサービスなど商談の中で専門性を証明することが必要」といったパターンでは、依然として生身の人間が関わる必要があると考えます。
これからのB2B営業に求められる「ハイブリッド型営業プロセス」
このように生身の営業担当者が顧客から求められるため、営業組織はAIと営業担当者を組み合わせたハイブリッドな営業プロセスを構築する必要がある、というのがレポートの結論です。
AI の効率性と生身の人間に対する需要とをうまく両立させるには、営業組織は両方の長所を活用したハイブリッドな営業プロセスを構築する必要があります。
第一に、スピーディーな情報収集が求められる定型的な初期段階の顧客対応は、AIツールで行うことです。これにより、営業チームは工数を確保しながら、より多くの問い合わせに対応できるようになります。
同時に、ソリューションのカスタマイズや、顧客との交渉など、購買プロセスにおける重要な接点を特定しなければなりません。これらの接点に熟練した人間の営業担当者を配置することで、購買担当者が求めるパーソナライズされた顧客対応と安心感を確実に提供できます。
まさに顧客の購買プロセスに応じてAIというハイテクと、生身の営業担当者というハイタッチを組合せる必要があるということです。これは、トライツがこれまで主張してきた「ハイテクとハイタッチを組み合わせた両利きの営業力」そのもの。「我が意を得たり」と思ったレポートでしたので、今回ご紹介しました。
特に日本では若手人口の減少が継続しており、構造的な人手不足が約束されてしまっています。定型化可能な営業プロセスの初期段階や少額の標準品の販売はAIやECに任せ、既存の大口アカウント対応や複雑/高額な商品の商談で専門性と生身の人間としての安心感を提供する、というハイブリッド化は日本のB2B営業において今後不可欠だと思います。
B2B購買(の一部)には人間相手のつながりと共感が不可欠
海外へのカンファレンスに出張すると、AI翻訳ツールを使って会話しようとする人たちを見ることがあります。確かに用件は伝えられるのですが、どうもぎごちなく、会話のリズムが崩れ、そしてなにより相手の人がつまらなそうな、もの悲しそうな表情をしているのが気になってしまいます。
私の英語は決して褒められたものではないのですが、それでも一生懸命伝えようと会話していると、相手はしっかり理解・共感してくれますし、人間同士で通じ合えている瞬間を感じることができるようにもなります。
B2Bの購買においても、おそらく同じようなことが起きているのだと思います。用は足りるものの無味乾燥なAI相手の情報収集と、共感やつながりを感じられる生身の営業担当者との会話。自分たちが購買担当者だとしたら、AIだけでなく生身の人間とやり取りしたくなるのは容易に想像がつきます。今回ご紹介したレポートはまさに、このような購買担当者としての思いを教えてくれているのだと思うのです。
皆さんの営業は顧客から求められる存在になっていますか?
ただ、ここで大事なのは、営業担当者は単に生身の人間であればよい、ということではありません。顧客として共感が得られ、理解してくれていると思え、なにより安心できる存在でなければ、生身の人間として接する意味がないのです。AIが顧客の最初の相談相手となるこれからの時代に、これまで以上に顧客から頼りにされる営業にならなければならない、ということではないでしょうか。
参考:「Top Trends for CSOs Impacting B2B Sales in 2030」(Colleen Giblin and Elizabeth Jones, Gartner, Inc., August 25, 2025)